Hot News
キャリア
2018.10.17
【卒業生訪問】アメリカで乳癌治療のガイドライン作りに奔走する オクラホマ大学スティーブンソン癌センター准教授 田中竹美博士
昭和女子大学を卒業後、一歩踏み出して行動し続ける女性を紹介するシリーズ。
今回は、乳癌を診断する「生検(せいけん)」が癌を増殖させることを発見し、手術までの日数などのガイドライン作りに尽力する田中竹美オクラホマ大学医学部病理学部・スティーブンソン癌センター准教授(1994年管理栄養学科卒、96年修士号取得)に話を聞きました。

国民皆保険制度が整っている日本では、乳癌と診断されればすぐに手術するのではないでしょうか。ところが、アメリカでは、一人一人加入している医療保険が異なります。手術に保険を適用するには認定が必要で手術まで時間がかかります。30%が2か月以内に手術を受けられません。
何万人ものアメリカ乳癌患者のデータベースを作成する中で、手術の遅れは貧困層だけでなく、高い教育を受けた高収入の富裕層にも見られることがわかりました。別の医者のセカンドオピニオンを求めたり、高名な医師の手術を待ったりして、時間がかかります。問題はどのくらいの期間内に手術をうけるべきなのか、ガイドラインがアメリカにはないんです。ですので今、アメリカで乳癌治療ガイドライン作りに取り組んでいます。アメリカの保険制度が少しでも変わってくれれば。何かの役に立つことが、研究の意義だと思っています。

2年後期に飯野久和先生の授業で、初めて顕微鏡で微生物を見たときに、すごく楽しくて。微生物を初めて見て、カタチやサイズや光り方も違うことに驚きました。最初に見た納豆菌は、棒状でまるでチョークのようでした。
3年で飯野ゼミに入り、大学院の修士まで実験室にこもりました。化粧もせず、買い物にもいかず、帰宅は連日終電間際。なぜか父は「彼氏でもできたのか」と心配したようです(笑)。
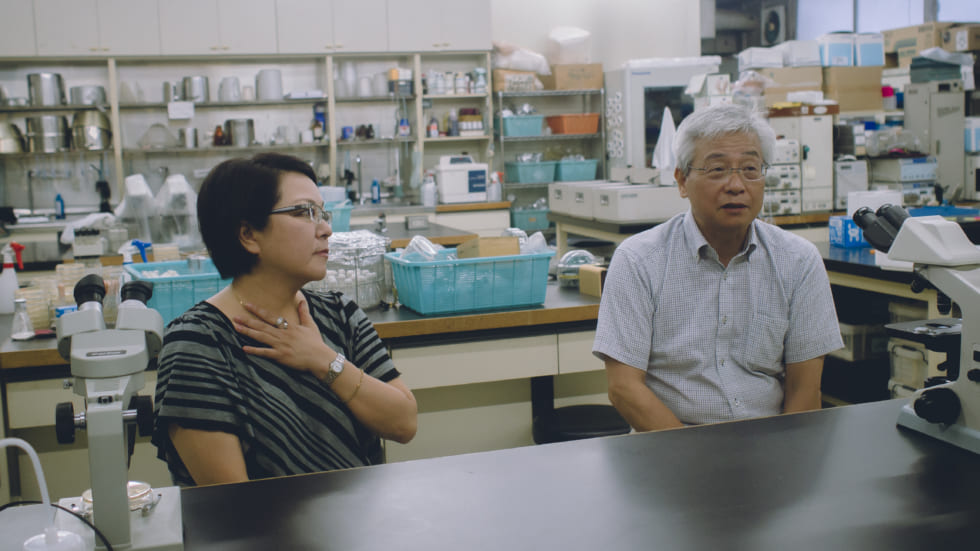
でも、英語ばかり勉強していたように記憶しています。大量の試験管を何時間もかけてつるつるになるまで洗浄する間、単語帳を目の前にぶら下げて覚えたり、夏休みに個人でアメリカに留学したり。4年のとき「英語は道具だから、何をしたいのか明確に」と言われたことで、英語はツールとして、そして研究に軸を置きたいと強く思うようになりました。徐々に研究のための英語の論文を読むのに抵抗がなくなっていきました。
卒論、修士論文は、インドネシアの発酵食品で微生物が出す酵素がテーマでした。いったんは企業に就職しましたが、生理学の研究がしたくなって、先生の紹介で静岡県立大学で博士号を取得しました。日本企業はポスドク(博士号取得者)をほとんど採用しません。たまたまアメリカ国立衛生研究所(NIH)から博士号取得者の募集があり、電話インタビューを受けて1999年、アメリカに渡りました。
取得できるデータ量や、スピードが増し、ビタミンAが乳癌の増殖を一時的に抑える過程を比較的短期間で解明することができました。以降、ずっと乳癌の仕事をしています。
アメリカでは研究費を獲得することが必須です。テキサス大学で、申請書を教授に代わって書くポストに就き、申請書の書き方や研究室の運営を身に着けて、2010年、公募でフィラデルフィアにあるトーマス・ジェファーソン大学に移り、初めて自分の研究室を持ちました。

採用は、まず書類審査で300-500通のうち10%に絞られ、インタビューに呼ばれるのは応募総数の1%くらい。私の場合は30-50件ほど応募し、10回ほどインタビューを受けました。複数のオファーからトーマス・ジェファーソンを選んだのは、勘です。昭和女子大と同じですね(笑)。今は私も選考する側ですが、選考の際に見るのは、考えるプロセスです。
このときの契約条件が、5年以内に研究者の登竜門ともいえるNIHの研究費「R01」を獲得することでした。研究者は2-3か月をかけて寝る間も惜しんで申請書に取り組みます。幸運なことに1年目に乳癌細胞増殖抑止治療法の研究で、R01約2億円(約195万ドル)の助成を受けました。研究の幅を広げるため、癌の研究で知られ、患者さんを主体とした研究(クリニカルリサーチ)ができるオクラホマ大学へ転職しました。
乳癌細胞と炎症の関係をテーマに、癌細胞がどんな場合に炎症を起こすか、研究室で議論を重ね、抗がん剤、放射線などと並んで生検が挙がりました。「そんなことありえない」と思いつつ、余っていたネズミの癌細胞を針で傷つけると、癌細胞が増殖して、転移する。
でも、動物実験をそのまま人間に適用することはもちろんできませんし、生検を否定しかねないような研究結果をそのまま世に問う訳にはいきません。癌の確定診断には生検は必須で、生検の結果、乳癌と診断されるのは約20%です。
目の前で見ている動物実験を、どう人間にあてはめるか。「ああでもない、こうでもない」と考える中で、ようやく、生検から手術までの時間に着目するという、研究するべき方向性が見つかりました。そこからの研究で、診断から2か月くらいまで変化が起きず、その先手術までの時間の経過とともに死亡率が上がることを突き止め、ガイドライン作りへとつながりました。
 飯野教授から学んだ研究の基礎
飯野教授から学んだ研究の基礎
研究する分野は変われど、プロセスは同じです。私のように研究の枝葉をどんどん伸ばしていくタイプは異色かもしれませんが、研究は1本道ではありません。異なるエリアの仕事を見たり聞いたりしないと、大きなかたまりが見えてこないのではないでしょうか。
大学時代は無心に自分のためだけに勉強ができる、とても贅沢な最後の時間です。大学生の皆さんには、一つでいいので、自分の中で達成したいテーマを見つけて、それに向けて、集中して取り組んでもらいたいです。そして世界中に“昭和の桜”を咲かせていきましょう。
 田中博士はこれからも”昭和の桜”を咲かせ続ける
田中博士はこれからも”昭和の桜”を咲かせ続ける
今回は、乳癌を診断する「生検(せいけん)」が癌を増殖させることを発見し、手術までの日数などのガイドライン作りに尽力する田中竹美オクラホマ大学医学部病理学部・スティーブンソン癌センター准教授(1994年管理栄養学科卒、96年修士号取得)に話を聞きました。

乳癌の「生検」の影響をアメリカで実証
絶対に間違えないでくださいね。「生検」が悪いのではありません。疑わしい部位に針を刺して癌かどうかを調べる「生検」は診断に欠かせない不可欠なものです。問題は、手術までの日数なのです。診断が出てから2ヶ月以内に手術をすれば問題ありません。国民皆保険制度が整っている日本では、乳癌と診断されればすぐに手術するのではないでしょうか。ところが、アメリカでは、一人一人加入している医療保険が異なります。手術に保険を適用するには認定が必要で手術まで時間がかかります。30%が2か月以内に手術を受けられません。
何万人ものアメリカ乳癌患者のデータベースを作成する中で、手術の遅れは貧困層だけでなく、高い教育を受けた高収入の富裕層にも見られることがわかりました。別の医者のセカンドオピニオンを求めたり、高名な医師の手術を待ったりして、時間がかかります。問題はどのくらいの期間内に手術をうけるべきなのか、ガイドラインがアメリカにはないんです。ですので今、アメリカで乳癌治療ガイドライン作りに取り組んでいます。アメリカの保険制度が少しでも変わってくれれば。何かの役に立つことが、研究の意義だと思っています。

顕微鏡でのぞいた微生物のとりこに
昭和女子大学に入学したのは、「勘」です。受験のために学校を見学して、「ここに入るだろうな」と感じました(笑)。でも、研究者になるなんて想像もしませんでした。「資格をとっておけば何かの役に立つだろう」と管理栄養学科を選びました。まだ国家試験はなく、大学を卒業するだけで資格がとれた最後の世代です。2年後期に飯野久和先生の授業で、初めて顕微鏡で微生物を見たときに、すごく楽しくて。微生物を初めて見て、カタチやサイズや光り方も違うことに驚きました。最初に見た納豆菌は、棒状でまるでチョークのようでした。
3年で飯野ゼミに入り、大学院の修士まで実験室にこもりました。化粧もせず、買い物にもいかず、帰宅は連日終電間際。なぜか父は「彼氏でもできたのか」と心配したようです(笑)。
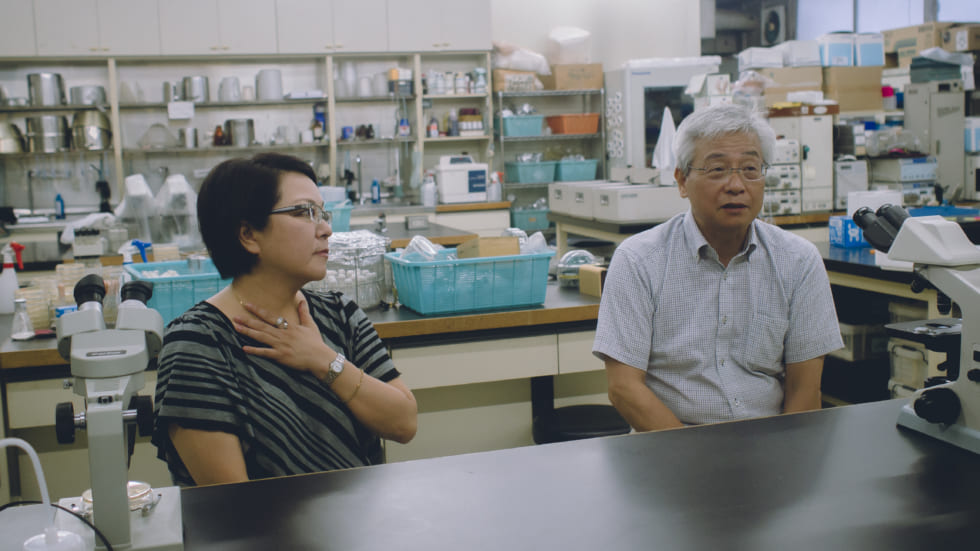
恩師である飯野久和教授(右)と
でも、英語ばかり勉強していたように記憶しています。大量の試験管を何時間もかけてつるつるになるまで洗浄する間、単語帳を目の前にぶら下げて覚えたり、夏休みに個人でアメリカに留学したり。4年のとき「英語は道具だから、何をしたいのか明確に」と言われたことで、英語はツールとして、そして研究に軸を置きたいと強く思うようになりました。徐々に研究のための英語の論文を読むのに抵抗がなくなっていきました。
卒論、修士論文は、インドネシアの発酵食品で微生物が出す酵素がテーマでした。いったんは企業に就職しましたが、生理学の研究がしたくなって、先生の紹介で静岡県立大学で博士号を取得しました。日本企業はポスドク(博士号取得者)をほとんど採用しません。たまたまアメリカ国立衛生研究所(NIH)から博士号取得者の募集があり、電話インタビューを受けて1999年、アメリカに渡りました。
アメリカで出会った乳癌
「乳癌とビタミンAについて、なんでもやっていい」。NIHに行くと、与えられたテーマはこれだけ。日本では試験管洗浄など準備に研究と同じくらいの時間を割いていたのが、アメリカでは研究のために必要なものは購入・外注し、100%時間を研究に使える。考えることがいかに大切か、目からうろこでした。論文を読む時間が倍増し、視野が広がり、どんどん研究が面白くなっていきました。取得できるデータ量や、スピードが増し、ビタミンAが乳癌の増殖を一時的に抑える過程を比較的短期間で解明することができました。以降、ずっと乳癌の仕事をしています。
アメリカでは研究費を獲得することが必須です。テキサス大学で、申請書を教授に代わって書くポストに就き、申請書の書き方や研究室の運営を身に着けて、2010年、公募でフィラデルフィアにあるトーマス・ジェファーソン大学に移り、初めて自分の研究室を持ちました。

採用は、まず書類審査で300-500通のうち10%に絞られ、インタビューに呼ばれるのは応募総数の1%くらい。私の場合は30-50件ほど応募し、10回ほどインタビューを受けました。複数のオファーからトーマス・ジェファーソンを選んだのは、勘です。昭和女子大と同じですね(笑)。今は私も選考する側ですが、選考の際に見るのは、考えるプロセスです。
このときの契約条件が、5年以内に研究者の登竜門ともいえるNIHの研究費「R01」を獲得することでした。研究者は2-3か月をかけて寝る間も惜しんで申請書に取り組みます。幸運なことに1年目に乳癌細胞増殖抑止治療法の研究で、R01約2億円(約195万ドル)の助成を受けました。研究の幅を広げるため、癌の研究で知られ、患者さんを主体とした研究(クリニカルリサーチ)ができるオクラホマ大学へ転職しました。
乳癌と炎症の関係からたどり着いた研究目標

乳癌細胞と炎症の関係をテーマに、癌細胞がどんな場合に炎症を起こすか、研究室で議論を重ね、抗がん剤、放射線などと並んで生検が挙がりました。「そんなことありえない」と思いつつ、余っていたネズミの癌細胞を針で傷つけると、癌細胞が増殖して、転移する。
でも、動物実験をそのまま人間に適用することはもちろんできませんし、生検を否定しかねないような研究結果をそのまま世に問う訳にはいきません。癌の確定診断には生検は必須で、生検の結果、乳癌と診断されるのは約20%です。
目の前で見ている動物実験を、どう人間にあてはめるか。「ああでもない、こうでもない」と考える中で、ようやく、生検から手術までの時間に着目するという、研究するべき方向性が見つかりました。そこからの研究で、診断から2か月くらいまで変化が起きず、その先手術までの時間の経過とともに死亡率が上がることを突き止め、ガイドライン作りへとつながりました。
昭和女子大で身に付けた多角的な見方
失敗した理由を、”多方面”、さまざまなアングルから考えるプロセスを学び、どうしたら成功する実験ができるようになるか、考える習慣は昭和女子大学で身に付けました。学生時代は実験で失敗することばかり。でも、飯野先生は失敗した理由を教えるのではなく、なぜ失敗したのか、砕いて、砕いて、考えることを習慣にするように導いてくれました。研究の基礎を身に付けられたことに感謝しています。 飯野教授から学んだ研究の基礎
飯野教授から学んだ研究の基礎研究する分野は変われど、プロセスは同じです。私のように研究の枝葉をどんどん伸ばしていくタイプは異色かもしれませんが、研究は1本道ではありません。異なるエリアの仕事を見たり聞いたりしないと、大きなかたまりが見えてこないのではないでしょうか。
大学時代は無心に自分のためだけに勉強ができる、とても贅沢な最後の時間です。大学生の皆さんには、一つでいいので、自分の中で達成したいテーマを見つけて、それに向けて、集中して取り組んでもらいたいです。そして世界中に“昭和の桜”を咲かせていきましょう。
 田中博士はこれからも”昭和の桜”を咲かせ続ける
田中博士はこれからも”昭和の桜”を咲かせ続ける