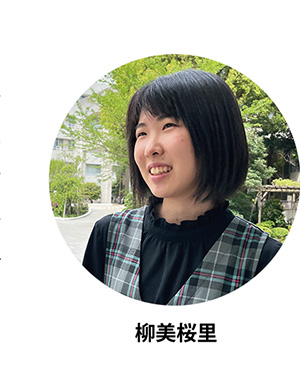|
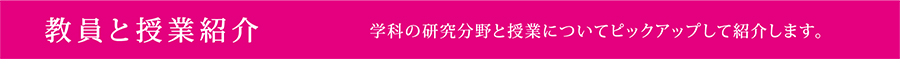

意識しなくても話せている日本語の文法について、ブラックボックスを開けるような気持ちで研究しています。パソコンの使いかたを「覚える」のとは別に、この機械中身を分解してみたい」という感じに近い興味を、ことばに対してぶつける感じです。 
|
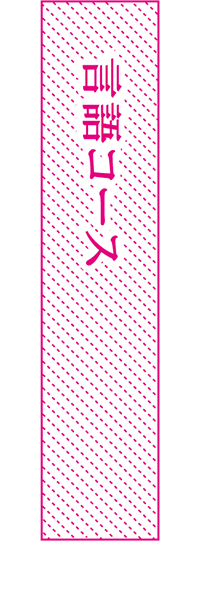
|

日常生活における実際の会話を収録・文字化し、普段はすぐに消えてしまう会話の特徴を客観的に分析しています。留学生の会話から外国人労働者の会話まで、現代社会の多様な異文化間コミュニケーションの特徴を明らかにし、その研究成果を日本語教育へどう生かすかを考察しています。 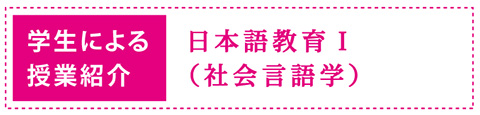
|

江戸時代の文学、なかでも近世実録と呼ばれる分野を研究しています。現代人が江戸時代の人物や出来事を語る時、そこには必ずと言っていいほど、近世実録の物語の影響が見られます。近世実録の〈もっともらしい嘘〉がどのように創られ、広まり、共有されたのか。この謎を解き明かそうとしています。 
|
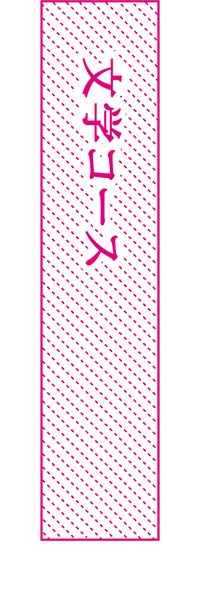
|

日本の児童文学のうち、時代で言うと明治から昭和前期にかけて、ジャンルで言うと女子を主な読者対象とした「少女小説」と、子どもに向けて書かれた「詩」を中心に研究しています。少女小説作家には女性も多く、女性の生き方という面でも関心があります。 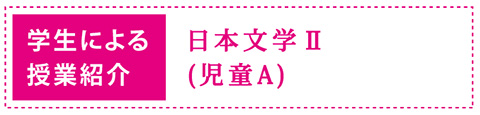
|

ことばがどのように変化し、なぜその変化が生じるのかを明らかにしたいと思い、今は日本語のゆれを中心に調査研究をしています。日本語が使われていれば、会話・小説・漫画・新聞・看板などすべてが調査対象。アンテナを張ってことばを観察しています。 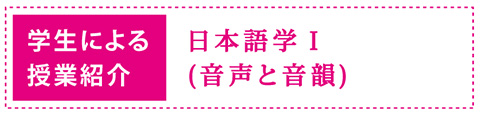
|
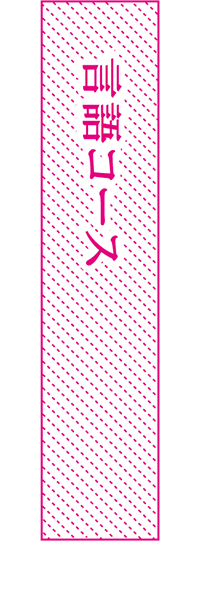
|

日本語母語話者と非母語話者が協働していく上で何が起こっているのか、どのようにすればいいのかを、主にコミュニケーションの場面から分析しています。日本語教育をその領域のものだけにせず、企業、官公庁、地域等と連携をしながら、より良い社会につなげるために研究をしています。 
|

『源氏物語』をはじめとする古典文学を、特に「呼称」に着目しながら研究しています。登場人物に用いられる多様な呼称からは、人物像や人間関係、ときには複雑な心情などをも読み解くことができます。変体仮名で残る和歌集や物語などの翻刻活動もしています。 
|
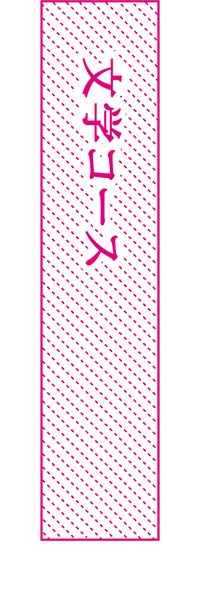
|

消費環境が急速に変化する中、物語を読む行為がいかに変化しているのかを研究しています。具体的に、小説では三島由紀夫、北杜夫、マンガでは藤子不二雄○、藤子・F・不二雄、アニメでは「機動戦士ガンダム」で著名な富野由悠季などを研究しています。 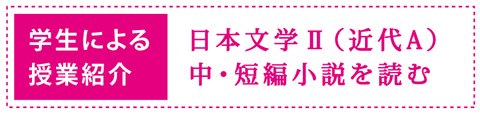
|

私たちの「つながっていたい」想いで広まるコミュニケーションとことばについて研究しています。最近では自身でLINEのコーパスを作成し、言語以外の要素をどう補いながら言語を使って円滑にコミュニケーションを取ろうとしているのか、その工夫について分析しています。 
|
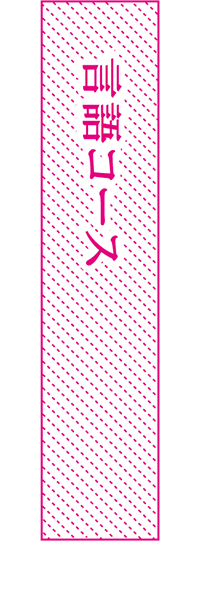
|
 |
||||||||||